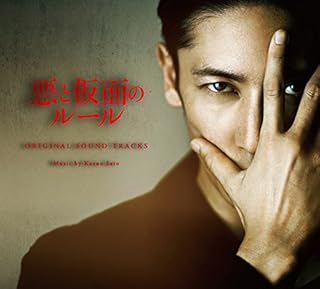自分の闇の世界に生きている、どうも、病んでる人こと青海ゆうきです。
中村文則さんの本を最初に読んだのは去年の終わり。
興味はあったものの、いや、興味がありすぎて、きっとこの人の作品を読んだら自分の中にある狂気が目覚めてしまいそうだと感じ、なかなか読めないでいた。
本や音楽は感情に直接働きかける強い力がある。
そして素晴らしい作品は人を生かすことも滅ぼすこともできるのだと僕は確信している。
もしかしたらそんな一冊になるかもしれない、と思った中村文則さんの作品「悪と仮面のルール」を紹介する。
「悪と仮面のルール」について
2010年6月に講談社創業100周年記念「書き下ろし100冊」作品として刊行されたミステリー小説。
英訳版 (EVIL AND THE MASK) が、ウォール・ストリート・ジャーナル紙の2013年ベストミステリーの10作品に選ばれるなど日本だけでなく海外でも評価の高い作品だ。
今年の1月には玉木宏主演で映画化もされた。
作者について
この本の作者、中村文則さんは1977年9月2日愛知県出身。2002年に「銃」で新潮新人賞を受賞してデビューし同作品は芥川賞候補となった。3年後の「土の中の子供」で芥川賞を受賞し、それ以降の作品は英訳版が海外で評価され、現在18ヵ国で翻訳刊行されている。
参考サイト:小説家 中村文則公式サイト -プロフィール-(更新2017年9月1日)最終閲覧2018年9月2日http://www.nakamurafuminori.jp/profile.html
内容
主人公は幼少期から邪の家系を継ぐ者として育てられる。
同じ家で過ごしている養子の女の子に好意を抱いていた主人公は、父によって女の子が損なわれると知り、女の子を守るために父を殺害しようと計画する。
成長していくうちに自分が父親に似てきていると感じ、殺人犯としての自分に決別しようと整形し顔を変え、他人の身分を手に入れて違う人間の人生を歩むことを決める。
しかし身分を変えても平穏な人生は訪れることなく、警察に追われることとなる。
レビュー
ニュースでは毎日のように誰かが殺されたことを報道し、殺人犯はまるで欠陥品のように扱われている。
被害者については可哀想だと同情の声が上がるが、加害者については厳しい世の中だ。
勿論、どんな理由があれ殺人は許されることではないが、自分が生きるためにやむを得ず殺してしまったとしても100%殺したほうが悪いと言えるのだろうか。
法律に反すること=悪という構図に疑問を抱く人が少ないと思うのは僕だけだろうか。
この作品は人間はどういう生き物なのか、悪とは一体何なのか、ということを読んだ人に問いかけているように感じた。
また、人を殺してしまった人間がどういう気持ちになるのか、どういう人生を生きることになるのか、ということについて主人公の心の葛藤が生々しく描かれている。
そして一人の人間の存在が主人公の人生を大きく変えているという点においては、ミステリーではなく純愛小説を読んでいるかのようだった。
mubook的評価
悲しい ★★☆☆☆ 切ない ★★★★★ 苦しい ★★★★☆ 暗い ★★★★☆ 重い ★★★★☆
合計 19/25★
病んでる度80%
映画「悪と仮面のルール」について
2018年1月に玉木宏主演で映画が公開されていてすでにDVD化されている。
ただ、人間の深い部分を表現している小説を映画化するのはなかなか難しい。
これまで純文学の小説を紹介する度に、映像化は難しいと散々言ってきたが、「悪と仮面のルール」もジャンルとしてはミステリーだが、純文学の要素が強いからか映像化が成功しているとは思えなかった。
【関連記事】純文学のレビュー
→小説「蛇にピアス」をレビュー。生きている実感を得るために。
それから、演技力云々ではなく、玉木宏は爽やかで良い人というイメージがあるからかこの作品の主人公のイメージとは違うかな、という感じがした。
音楽を楽しみたい人には
映画の評価はいまいちだが、サントラはかなり良い。
重々しさや緊迫感、物悲しさがある曲で小説も映画も見たことない人でもこのブログに興味があって見てくれている人にはオススメのアルバムだ。
普段クラシックやサントラを聴く人にはとくにオススメ。
まとめ
中村文則さんの作品は、人間の内側をグロテスクに描いている作品が多く、普段見て見ぬふりをしていたい感情をも呼び起こしてしまいそうになる。
「悪と仮面のルール」は殺人を軸に一人の人間の人生の一部を描いている作品だ。
他人の人生を生きるということについて書かれている点では、松本清張の「砂の器」を彷彿とさせる。
ミステリー好きよりも、純文学や哲学が好きな人におすすめする一冊。
是非「悪と仮面のルール」を読んで、本当の悪とは何なのかを考えてみてもらいたい。