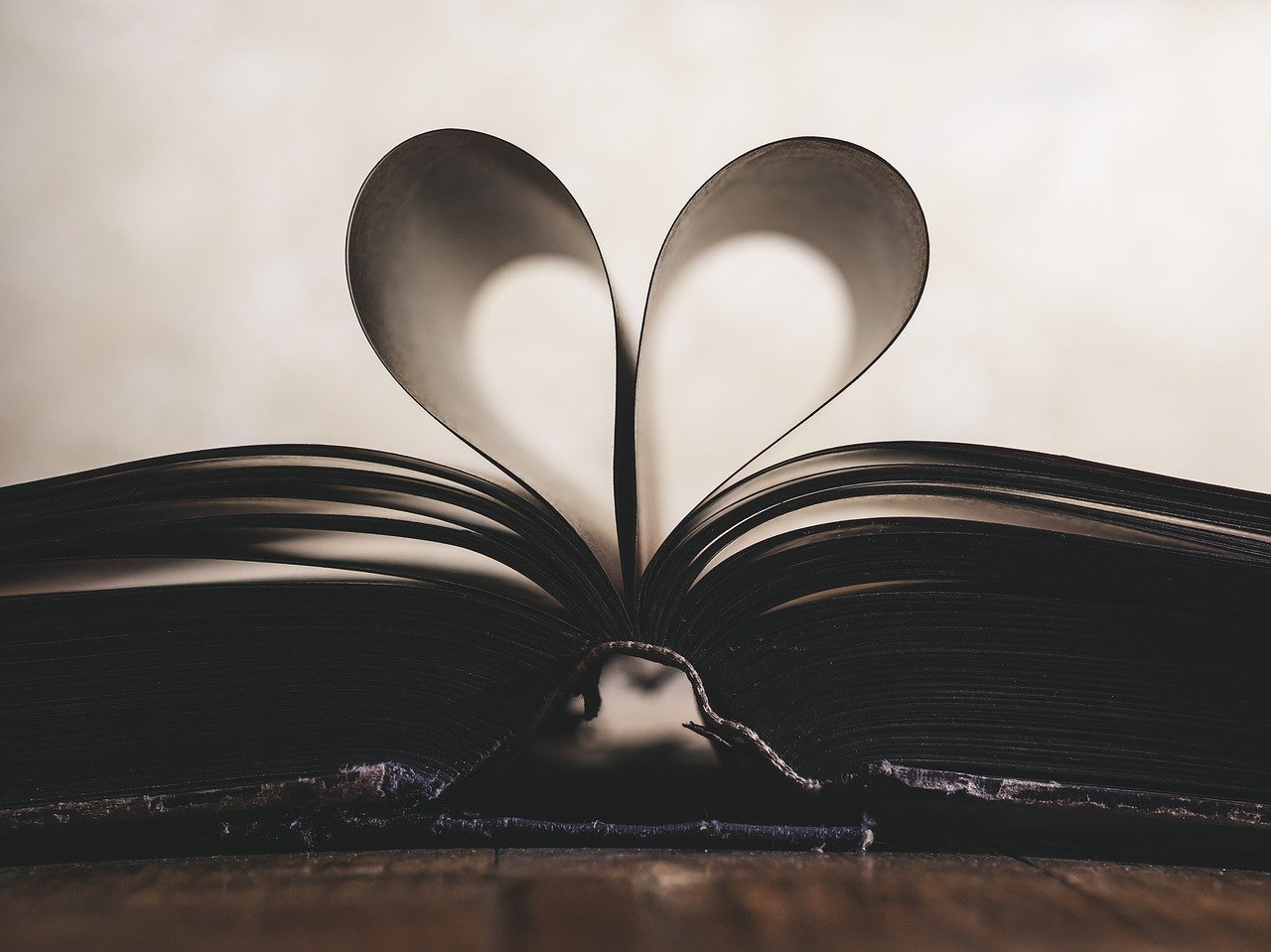顔色が悪いのがデフォルトの青海ゆうきです。
2月にTwitterのフォロワーさんが3000人を超えて記念企画をすることにした。
詳しくは→フォロワーさん3000人突破企画について
をご覧ください。
たくさんのご協力と応募をありがとうございました。
それでは早速本編をどうぞ。
フォロワーさんが選ぶ2018年に読んで良かった本
応募をいただいた順番に紹介。
感想をいただいた方のTwitterへのリンクを貼っているので繋がりたい人はフォローするがよろし。
「私が笑ったら、死にますから」と、水品さんは言ったんだ。/ 隙名こと
父親が亀に当たって死んだ、という衝撃的な一文にいきなり掴まれます。
故あってクラスで陰キャポジションである男子高校生駒田くんが、不登校気味のクラスの美少女水品さんに巻き込まれて展開していく青春ストーリーです。
ミステリーではあるけれど、人が死なない程度の日常物。米澤穂信の『氷菓』シリーズや、初野晴『ハルチカ』シリーズが好きな方は楽しめると思います。何よりヒロインの水品さんが可愛い。駒田くんも何だかんだで健気で全うに生きていていじらしいのです。
理不尽なことに対して正義感を振りかざしたくても、自分なんかが、、って、弱気になることは多いです。そうするには何か資格が必要で、そしてただ誰も傷つけずに生きてるだけではその資格に足りない気がどうしてもしてしまう。そんなモヤモヤを抱えている子に一歩寄り添ってくれるような物語でした。オススメです。
あとTwitterで作者の隙名ことさんと尋常ではないほどコミュニケーションが取れます(笑)
ひでじ@九州/@hideji_NTG さんより
隙名ことさんは僕もフォローしている作家さんだ。
Twitterでもよく『「私が笑ったら、死にますから」と、水品さんは言ったんだ。』の感想や読了ツイートを見かける。
それは紹介者の感想にある通り、著者の隙名 こと(すきなこと)さんと気軽にコミュニケーションが取れるということから、応援の意味も込めて読者がツイートしているのではないかと思う。
作家は孤高で気高き存在、というのはもうひと昔前の話なのかもしれない。
去年の暮れに米澤穂信さんの「氷菓」を読んだばかりだが、いつも重々しい小説ばかり読んでいる人には息抜きに丁度良いのではないだろうか。
表紙がライトノベルのようだとつい敬遠してしまう僕だが、読んでみると意外と面白かったと思うことも多い。
「私が笑ったら、死にますから」と、水品さんは言ったんだ。/隙名 こと
症例A/多島斗志之
一種のサイコミステリーではあるけれど、大きな2つの物語が並行して進み、最後には違和感なく一つに重なる。
精神科医と臨床心理士との確執など、リアル過ぎる描写が素晴らしい。「精神科医を弄ぶ17歳の少女」
これだけで、ご飯おかわり出来ます。
かめさま@やさぐれ読書日常垢/@ksaikamone0120 さんより
「精神科医を弄ぶ17歳の少女」というフレーズを見たとき、これはもしかしたら僕の病気か、それに近いものの話なのではないだろうか、とピンときた。
予想通り、精神科医は「境界例」の疑いを持ち、臨床心理士は「解離性同一性障害」の可能性を指摘する。
個人的に紹介された本の中で一番興味がある本だ。
多重人格といえば、ダニエル・キイスの「24人のビリー・ミリガン」、国内のサイコミステリー小説と言えば貴志祐介さんの「悪の教典」「黒い家」などが有名どころだろうか。
この「症例A」の内容も気になるところだが、著者の多島 斗志之(たじまとしゆき)さん、2009年に両目の失明を苦に失踪したというのが驚きだ。
幻想古書店で珈琲を あなたの物語/蒼月海里
本や人との縁を失くした者の前にだけ現れる不思議な古書店『止まり木』シリーズ完結巻。始まりがあれば終わりもあって、永遠はないからこそ大切な人を見失わないでいたい、その大切さをシリーズを通して実感しました。
あとがきにて『この作品は書店員として私の手作りポップと言っていいかもしれません』とおっしゃっていたように、今まで触れなかった作品との出会いに誘われました。有名な古典文学から近代文学まで多くの作品が取り上げられ、それぞれ物語の受け取り方、読み方、考えの違いを知ることもできて更に読書の幅が広がりました。
この本に出会えて本当に良かった。たくさんの縁との巡り会いに感謝します。
双子moon読書垢/@moon61226676 さんより
「幻想古書店で珈琲を」はシリーズものの小説で、全7巻。
本を題材にした小説と言えばドラマにもなった「ビブリア古書堂の事件手帖」が記憶に新しい。
本好きであれば、本が題材の小説は楽しめないはずがない。
海外古典から近代文学まで幅広く登場するらしいので、新しい本との出会いや発見がありそうだ。
70年分の夏を君に捧ぐ/櫻井千姫
2015年の夏、東京都に住む高校二年生の百合香。1945年、戦時中の広島で日々の生活を送る千寿。
百合香と千寿は、夢の中で不思議な体験をする。朝、二人はお互いの体が入れ替わっている事実に直面する。設定的には、同地域での入れ替わりが普通だが、この作品は、東京と広島とで地域が違う。このところが、重要な要素であり、読み進めていくと納得できる設定であった。
広島の原爆投下前日、千寿、百合香ともに選択を迫られる。そして、原爆投下。二人は、それぞれの葛藤を乗り越え、自分なりの導き出した答えに従い行動する。その姿は涙を誘う。百合香の友人が軽い設定な分、千寿の友人、菜穂子は好印象を持つ。彼女の生死も気になる作品。
蛍雪/@@eM6Ar2JW8vb7n5I さんより
二人の人間の入れ替わり、という設定はこれまでにも多くの小説で使われてきた設定だ。
東野圭吾の「秘密」、池井戸潤の「民王」、森絵都の「カラフル」、小説ではないが大ヒットしたアニメ「君の名は。」など。
こうした人格の入れ替わりを設定にした物語は、本来知ることのないことを知ったらどうなるのだろうか、という疑問と好奇心を揺さぶられる。
設定は同じでも、入れ替わる二人の関係性、人間性、時代性によって話は全く違うものとなる。
入れ替わりものということより、どんな二人が入れ替わるのか、ということに注目してほしい。
DADAROMAのおすすめ曲とアルバムを紹介の記事でも書いたことだが、僕は広島に近いところで生まれ育ち、原爆ドームにもよく行っていたので原爆が題材にされたこの本は個人的に気になる作品だ。
夏と花火と私の死体/乙一
この本は乙一のデビュー作であり、当時17歳であった作者が初めてジャンプノベル大賞を受賞した作品。
正直この本を読んだとき驚いた。タイトルに”夏と花火”とある通り”花火”が打ち上がるシーンがあるが、この”花火”を表現する言葉やフレーズがとてもリアリティと臨場感、まるで小説内に自分が入り込んだように感じるほどであった。それを自分とあまり年の離れていない時期に書いたとは思えない。世界中どの17歳を探してもこれほどの表現力を持つ17歳はいないんではないかと。
でも、単純なストーリー性には、やはり17歳なんだと思うところもちらほら。それも含めて17歳の乙一にしか書けなかった本だったと思う。
周/@SHU0603OTSUICHI さんより
「GOTH」シリーズは第3回本格ミステリ大賞を受賞し日本とアメリカで映画化されたこともあり有名だ。
「GOTH」はライトノベルとして連載されたものを一般小説として書籍化。そのことについて「ライトノベルのままでは手にとってもらえない客層がいるという事実を覆せなかったという点では、ある種の敗北である」と「失はれる物語」のあとがきで述べている。
今回この記事で紹介している本は(たまたま)ライトノベルの分野や携帯小説から書籍化された本が多い。
たしかにライトノベルは僕のように敬遠する人間はたくさんいるし(今は割と手にとるようになった)、表紙がアニメタッチというだけで見向きもしない人がたくさん存在する。
乙一さんといい、米澤穂信さんといい、ライトノベル分野から一般小説(とくにミステリー)へ行く人がいることをもっと多くの人が知れば、ライトノベルだから読まないという読まず嫌いももしかしたら減るのかもしれない。
ライトノベルというのは一般小説と何が違うのかという定義も曖昧で、ライトノベル=稚拙ということではない。
僕の経験上、一時期流行った携帯小説(恋愛ものでだいたいがカップルのどちらかが病気をする)ものを除けばライトノベルだから面白くなかった、ということは一度もない。
話が脱線してしまったが、そんな乙一さんのデビュー作は17歳での出版。
まだライトノベルだ一般小説だ、売れ行きが、なんて気にしていなかった頃の乙一さんのある意味純粋な作品なのではないだろうか。
猫を抱いて象と泳ぐ/小川洋子
今まで読んだ作品の中で1番好きかもしれません。小川洋子さんの作品は、いつも世界観が独特で圧倒されるんですが、これは今までを軽々と超越し、容易に作品の中に吸い込まれます。
チェスの話ですが、チェスが全く分からなくても何ら問題なく楽しめ、主人公がチェスの海を漂うさまに誘われ、気付けば自分が泳げないのも忘れて同じ海に潜り込んでました。
読み進めていく中でタイトルの意味を何度かに分けて理解する事になる。全てが繋がっているようで、どれも曖昧な主人公の思い込みが繋げてる、そんな少し物悲しく不思議な作品
K/@L1ke_a_child さん 2018年10月22日の投稿より
タイトルからしてとても不思議そうな作品。
小川洋子さんの作品は学生時代に「薬指の標本」を早稲田大学で小川洋子さんと同期だったと自慢していた教師から借りて読み、社会人になったあと「博士の愛した数式」を読んだが、どちらも好きな作品で紹介にある通り独特な世界観で作品の世界に入り込んだ記憶がある。
将棋、チェス、ポーカーなどボードゲームが好きなので「猫を抱いて象と泳ぐ」はチェスの話というところも気になった。
ポイズンドーター・ホーリーマーザー/湊かなえ
この恐ろしい結末が、ほんの些細なすれ違いで生み出されたなんて…
仲間内で、男と女で、母と娘で、正義と善意がすれ違う。同じ事実なのに、両者の解釈はまるで異なる。パラレルワールドを生きているかのよう。
そうしたすれ違いや思い込みが引き起こす結末の、なんと恐ろしい事かー。
あれ、ひょっとして自分とあいつの間でも…と我が身を振り返らずには居られない。
だい※固定ツイお願いします@本好きな関西の大学生/@dai_reading さんより
湊かなえさんと言えば「告白」。小説も読んだし、映画も観たが身近な出来事をまるでホラーのように恐ろしく描いている作品が多い印象だ。
イヤミス(後味の悪いミステリ)の女王と呼ばれるだけあり、紹介者の感想からも伺えるがきっと読後に気持ち悪さが残るのだろう。
「ポイズンドーター・ホーリーマザー」は短編集なので気軽に読めそうだが気軽に読むと作品の毒を倍ぐらいに感じるかもしれない。
屍人荘の殺人/今村昌弘
ミステリーなんですけどSF?ホラー?のような異色の作品だと思いました。
正直、こんなタイプのミステリー読んだことなくて途中戸惑いました。だって。推理小説だと思って読んでいったら、途中でゾンビがでてくるんですよ。
しかも、事故ではなくて殺人がおきる。やったのは、ゾンビか人か。
最後の最後まで、驚き!でした。
つちのーし@読書垢/@bookordead さんより
デビュー作にして『このミステリーがすごい!』 2018年、週刊文春 2017年ミステリーベスト10/国内部門、『2018本格ミステリ・ベスト10』、で1位を獲得したミステリー小説。
~荘の殺人というタイトルはよく見かけるので、この小説も例にならってクローズドサークルか、と思いきやゾンビの登場。
小説ではあまりないパターンだったかもしれない。
僕の大好きな映画「サイレント・ヒル」もそういえばミステリー×ホラーの作品だ。
神木隆之介主演で映画化もされ、続編の「魔眼の匣の殺人」も先月発売されたばかりの今最も注目されているミステリー小説ではないだろうか。
若きウェルテルの悩み/ゲーテ
読みながら、「死」と「愛」について考えた。
ぼくはまだ、「死」を体験はおろか触れたことすらない。そんな状態で「死」について考えるのはおかしく見られがちだけど、ウェルテルはそれに勇気をくれた。
自分の「愛」を確信するのはこわいことなのに、登場人物たちはそれを強く信じていて、それによって行動していた。人間の模範にしたいと思った。
鱒子 哉/@masukokana さんより
鱒子 哉さんのnoteはこちらから
マスメディアの自殺報道に影響されて自殺する人が増えるということを「ウェルテル効果」と言うが、その言葉の起源となったのがこの小説だ。
音楽の授業でシューベルトの「魔王」や「野ばら」を習った人も多いと思うが、これらの曲はゲーテの詩にシューベルトが曲をつけたものだ。
クラシック界では詩人として知らない人はいないと言っても過言ではないが、西洋文学では文豪としても名高い。
今でも多くの人に読まれている作品には時代が変わっても愛される普遍性があり、芸術性があり、人の心を大きく揺さぶる何かがあると僕は思う。
若きウェルテルの悩み/ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
「番外編・友人が選ぶ2018年に読んで良かった本」
「フォロワーさんが選ぶ2018年に読んで良かった本」はTwitterのフォロワーさんからの応募で無事1つの記事になった。
この企画を始めた時、僕はある友人にも同じことを聞いてみたいと思いラインで「2018年に読んで一番良かった本の感想を送ってほしい」と依頼した。
読書好きな僕だが、僕の友人や知人には読書好きがほとんどいない。
唯一、本を読んでいるこの友人に(しかも結構ヘビーな本を読む)聞かないではいられない、ということで最後に「友人が選ぶ2018年に読んで良かった本」を紹介する。
居酒屋/エミール・ゾラ
貧しい人々の生活の匂いが立ち込める19世紀後半のパリで、女の人生が不運と弱さと醜さのフルコースで描かれる。救いはなく、エピソードを読み進めるごとに嫌な記憶がよみがえるのに読むのがやめられない、小説としての強さがある。
作者ゾラは、この容赦のない悲惨な小説を、「私の作品の中で最も道徳的」と述べたという。目をそらさずに、人間の暗い本性が作り出した暗澹たる社会をひたすら観察し、正確に理解する。その努力を積み重ねた先に、惨めに死んでいった人々が救われる未来への希望があると信じていたのだろう。
かよへい/@kayoheion2ndbs さんより
この小説を選ぶ友人のセンスと感性には脱帽せざるを得ない。
エミール・ゾラはフランスの自然主義文学の定義者だ。
自然主義文学というのは、誇張表現などを用いず事実をありのまま描く文学のことで、リアリズムの一種だ。
日本では自然主義文学はあまり浸透しなかったが島崎藤村の「破戒」や田山花袋の「蒲団」「田舎教師」などがこれにあたる。
もっと簡単に言えば正確なカテゴライズではないが、「渡る世間は鬼ばかり」のような日常を淡々と描いているものや、高畑勲監督の「火垂るの墓」のような作品も自然主義的だ。
事実と客観性を突き詰めた作品には空想や想像以上の説得力があり、人間がつい目をそむけたくなる隠された真実を見出す力がある。
それはとても平凡で、とても日常的で、とても残酷なものだと思う。
さいごに おまけつき
今回応募いただいたフォロワーさんに今年読みたい本を聞いてみたので紹介する。
具体的な作品名を出してくれた方からは
・「ひと」小野寺史宜
・「あなたの罪を数えましょう」 菅原和也
・『「後日談SSのふりーぺーぱーです」と、水品さんが言っています』隙名こと
・「自由からの逃走」エーリッヒ・フロム
(順不同)
の名前が上がった。
昔影響を受けた遠藤周作の本を読み返したいという人や、太宰治の「斜陽」をたくさん読み返したい、ドフトエフスキーのものを読みたい、という人もいた。
最近出版された本や名作を読み返したい人が多いようだ。
今回応募いただいたフォロワーさんは僕なんかよりずっと読書家であると思うので、今年読みたい本は?という質問の返答に困った方も多かったかもしれないが、感想も含め企画に参加いただいたことを心から感謝いたします。
本当にありがとうございました。
またこういった企画をすると思うので、良かったらまたご参加ください。
今回参加できなかった方も、タイミングが合えば是非どうぞ。
それではまた。